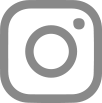niime 百科
niimeゆく年くる年 2021-2022
〈 くる年編 〉
〈 くる年編 〉

2022 . 01 . 01
皆さま、新年明けましておめでとうございます! 本年・2022年も、「niime百科」をどうぞよろしくお願いいたします。
〈大晦日「ゆく年編」からの続き〉
玉木「明けて2022年、「tamaki niime shima」が新たにオープンします!」
—— そうですよねぇ、いよいよ2月にスタートすると。…って、ここで言っちゃって大丈夫ですか?
玉木「うん。有言実行にしよう。2.23に決まりました!」
—— 2月23日ですか!
玉木「23日は日取り的にも良いらしくて。それで、語呂がいいから、2022年2月22日プレオープンにしようと思ってて。」
—— おおっ!2ならびで…。
玉木「私が思うに、やっぱり2022年は、「嶋」がキーだと思ってる。これまでつながってなかったところが、「嶋」を起点として、ひとつにつながるような絵が見えてる。」
—— 新たに誕生する「tamaki niime shima」が、色んなモノ・コト・ヒトを結ぶひとつの拠点となるわけですね。
玉木「うん。「niime村」の玄関口としても機能するし。…以前西脇の街中にいたでしょ?それが2016年に加古川のこちらにShop&Labを移転して、あっちはあっち、こっちは こっちって、自分の中でも分断したところがあったんですよ。」
—— 川むこうだなぁ…と。
玉木「あちらは都会ですね…みたいな(笑)。でも離れたままじゃ色々うまく回っていかないから、つなげるところも大事で。中心部から離れてる間に市役所も新しく出来て街中の播州織工房館の辺りも色んなお店が増えてきてどんどん面白くなってきてるから、そこともしっかりつながって、西脇全体が面白い場所だよってPRもきちんとしていきたいなぁって想いもあるので。」
—— 新しい「嶋」のお店は国道 175号線沿いですしね、立地的にも色んな人の目に留まりやすい。
玉木「そうなのそうなの。市役所からも遠くない市の表玄関近くに看板出せるってゆうのはすごく大きいから。そこからまだ出逢えてない人たちにも発信していけたら良いなと思っています。」
—— なるほど、「tamaki niime shima」オープンの狙いがよくわかります。
玉木「町田をもっとよくするためにも「嶋」を創ろうという想いもあった。「嶋」で布をわかる人が布をしっかりと伝えて販売する、そのモデルを町田に落とし込むことで流れをつくりたいというか。もっともっときちんとオモシロイものを提案してゆく仕組みを構築したい。オンラインでも生地の販売はまだこれからだから。そこを含めて、2022年はやりますよ。」
—— まずは「嶋」で実験してみて、という感じですか?
玉木「「嶋」で、「町田」よりももうちょっと布の数を増やして、コーナーを大きくして、オンラインでも販売できるような仕組みを創ろうと考えています。」
—— とても愉しみです。
玉木「会社全体的なところに関して言うと、去年の6月くらいから、インナー・ブランディングということで、tamaki niimeの「ミッション」や「ビジョン」を言葉にして明確にしてそれを掘り下げる作業をやったんですけど、各チームの中で自分たちがどうあるべきか?の話し合いをしっかりできた、ってゆうのがよかった。行動に実際に移すところはまだまだこれからなんですけど。」
—— チーム内で議論して、これからの「アクションプラン」を各チームが言葉にできたというわけですね。
玉木「今まではそれぞれの個人プレーで社内的にはうわべの付き合いだったところが、どうあるべきか?っていう“哲学的な”部分を一緒に話し合う時間を持てたということで仲間意識はすごく強まったと思う。まだまだこれから、もっとこうしようああしようと掘り下げていく時間が大事だけど、この半年間の取り組みがあるのとないのとでは全然結果は 違ったと思う。」
—— 「アクションプラン」の発表の場を私も共有させていただいたんですが、tamaki niimeを貫くミッション=「ちきゅうの ゆがみを ととのえる」、そして「niime村の創造」というビジョン、「まいにち ぜんぶ たのしむ」という行動指針が定まったことで、それらの言葉に基づき具体的な行動をチームとして考え実行してゆく「アクションプラン」という土台が出来たわけですね。各チームの取り組みにも一本筋が通った印象があります。
玉木「発表して言語化したことで、スイッチが入るというか。そっちに向かってゆくという実感はあるかな。」
—— 以前からtamaki niimeとして、「地球」にとって…という活動の物差しは持っていたわけですけど、チームごとに皆んなで寄ってディスカッションしながら考えて、そこにどうアプローチしてゆくか、っていう部分がすごく明確になった気がします。
玉木「皆んなピンときた、っていうかね。まだまだ、実行の段になってどうやっていくんだ?ってところを決めかねてはいるけど。」
—— 具体的な方法論のところですね。
玉木「肝心の「niime村」ってなに?ってところが皆んなまだぼんやりしてるというか。これだ!と決めてしまう必要は全くないんだけど、皆んな、それぞれに言語化がまだできてないのよ。」
—— そこは異なっていて良いから、それぞれに落とし込んでほしい、っていう…
玉木「うん、自分だったらこうしたい!っていう、こうゆうのがniime村じゃない?っていうのを発言し合うことで…」
—— ディスカッションが生まれますし。
玉木「…見えてくるものがあって。だったらこうじゃない?とか、プロジェクトを開始にあたって、そこを語り合う時間を持とう、と。そうすると実際に2022年からはもう少し具体的に、チームとしても個人としても動いていけるんじゃないかと。」
—— その語り合いってすごく愉しい時間になりそうですね。
玉木「真っ白な図面を前にして、私こうする僕ああするって言い合う時間になるからね。そうなればワクワクするし。北海道にある旭山動物園(※)もスタッフ皆んなで絵を描いたそうなの。」
※北海道旭川市にある日本最北端の動物園。平成時代前半には入場者が減少していたが、動物本来の能力を引き出す展示手法や野生に近い環境づくりなど独創的なアイデアと工夫でリニューアルを施し、リピーターも数多い大人気観光スポットとなった。
玉木「こんな動物園あったらいいよね、面白いよね、っていうのを全員に書いてもらって、それを一個ずつ実現させてるんだって。だから今、すごい人気があるんだって。」
酒井「うん。」
—— それはモチベーションにもすごくつながる話ですよね。“自分ごと”化するでしょうし。
玉木「アイデア出して実際にやってみたらすごい愉しいと思うから。そんな時間を持ちたいと思っております。それで決まれば愉しみだね。」
酒井「うん。」
—— “わがniime村”を想い描きつつ話し合うことで、2022年のワクワクがどんどんと広がる気がしますね。さて、次回の「niime百科」、この年越し取材に続いては、新しく「プロジェクト・リーダー」となった山下さん・藤田美緒さんへのインタビューが控えてるわけなんですが。
玉木「世代交代かなって思って。」
—— 2022年を委ねよう、という想いを持っておられるのかなと。
玉木「…いつ頃だろう?ここに来て5年だから…その前の上野にShopとLabが出来た時かな?だから8年前くらいか…。」
—— 上野の立ち上げの頃…7、8年前ですか?
玉木「その時に、スタッフもかなり増えて、もうtamaki niimeは玉木新雌ひとりで創ってるんじゃないんだから、もうこれ以上、私が創ってます!っていうような打ち出しをやめたいって騒いだ時があったの。取材に来られても、私が自ら織ってます!って風には出したくないと。」
—— そこは酒井さんと話し合ったわけですか?
玉木「うん、酒井と。これからは、作家というポジションで私が創るというんじゃなくて、皆んなで創っているってゆう、チームとして仲間と創ってるんだってことをちゃんとPRしていきたいから、って言ったんだけど、実質的にそれは叶わなかったの。」
—— といいますと?
玉木「例えばテレビの取材が来ても、玉木さんが織ってください、玉木さんがインタビューに答えてください、玉木さんの想いを聞かせてください、って当時はそんな伝え方を望まれて。」
—— 玉木さん個人にフォーカスされがちだったわけですね。それは自らショールを開発して数年が経過した頃ですよね。
玉木「そうです。だから、これからひとりじゃ絶対立ち行かないから皆んなで創る、ってスタッフを増やして行った時だったし。」
—— tamaki niimeの今につながる、スタッフとの新たなモノづくりの黎明期だったわけですね。
玉木「こっちに引っ越してきたら、私はもう創ってないんですよ、皆んなで創ってるんですよ、ひとりひとりが自分らしく立っている、そんな仲間でtamaki niimeは出来上がってるんですよ、と、誰が見てもわかるようにしたい、というのがその頃の夢だったんですよ。」
—— はい。
玉木「もちろん、こっちに来てShop&Labを始めたからってすぐにそうなれたわけじゃなくて、やっぱりまだまだ出来てなかったこともすごく多かったけど…少しずつ、日に日に、スタッフひとりひとりが成長して行って、チームごとにすごい個性が出てきて。」
—— ええ。
玉木「…皆んな一人前になってきたな…と、思いきや、隣のチームのこと考えずに暴走したりとかね、そんなチグハグだったりする問題も繰り広げられつつ、やっと2022年になる今、あ、ついに、tamaki niimeがひとつになってきたな…という実感はあるの。」
酒井「あるある。」
—— 「niime百科」の歴史を振り返っても、玉木さんの言葉の端々に歯痒さが滲んで感じられる時があった気がします。
玉木「なんでこうならないの…??、って。」
—— それがなんかコロナ以降変わってきたな…というか。
玉木「結局のところ、何が変わったか?っていうと、“私が変わった”のよ。」
—— あ、私が。人が変わるんじゃなくて。
玉木「自分が変わるんですよね。」
—— …。
玉木「もう、なんでやってくれないの??っていう被害妄想的な感じだったのよ。自分のこと棚に上げて相手ができてないっていう押し付けだったんだけど、あ、そうか私ができてなかったんだっていう(笑)ことがわかったんやな?コロナでな。」
酒井「うん。」
玉木「ありがたいことです。」
—— それは上に立つ者としての自分を省みてということですか?
玉木「酒井に言われるんだけど…「リーダーですべてが決まる」ってね。」
酒井「うん。」
玉木「リーダーがどれだけの器か、どういう想いがあってどんな会社にしたいか?によって色も規模も全部決まっちゃうんだよ、と。」
—— うぅ~ん…。
玉木「だから私が成長しなきゃいけないんだと思って。下を成長させようとするんじゃなくて、私が上に昇っていかない限りはそれに連れて皆んなも一緒に上がっていけないから。」
—— 自らステップを上がって、後に続く人のためのスペースを空けるという感じでしょうかね。
玉木「私が何かを教えるんじゃなくて、自分が上に昇るしかないんだと。そういう意味じゃ自分のクオリティをもっと上げなきゃ、というところに集中することで、ヘンに目クジラ立てて皆んなの様子を注視するようなこともなくなったし、そんな時間がないってゆうのもあるけど、したら結果的に皆んな自分たちでしっかりと自分たちの仕事を全うするようになるし、チームリーダーもそれぞれがやるべきことを掘り下げて行けるようになったから。…私だったんだな、ってところですよ。」
—— そこは藤本隆太さんにインタビューした時にも伺った“委ねる”というところにもつながる部分でしょうかね。「織り」にせよ、社長の玉木さんからスタッフへ、また次のスタッフへと引き継いでゆく。そんな流れが今形づくられてきてるのかなと。
玉木「次の世代につないでいかないと、やれることも増えていかないからね。常に新しいことをやろうとするし、仕事はどんどん増えていくからね。」
—— う~ん…。
玉木「つなぎつつ、新しいこともやりつつ。たくさんの新しい仲間を増やしていくことも同時にやっていかなきゃならないから。忙しいのは忙しいんですけど、でもその方が常に動いてるわけだし。川とかもそうでしょ?常に水は流れてて、滞っちゃ駄目でしょ。」
—— 澱んじゃいますからね。
玉木「澱まないように流れをつくる、ということで色んなことにチャレンジして、成長し続けていけるといいよね。」
酒井「うん。」
—— ある時点からあまりお尻を叩くって感じじゃなくなって、変わったっていうことですかね。
玉木「そうだね、叩いてない。勝手にやってるよ皆んな。」
2021年、この地域の伝統産業である播州織の価値を捉え直した一点モノのモノづくりと、そこから広がるコットン栽培をはじめとする、この産地における循環的な取り組みの総体が評価され、tamaki niimeは「グッドデザイン賞」を受賞した。玉木によれば、それは自ら望んで応募したわけではなく、スタッフからの提案によるアプローチだったという。
玉木「私個人はあまり人からの評価を気にしない質(たち)なんですけど、今回はスタッフの藤本君が応募したい、という意思を伝えてくれて。藤本君と久保君がプレゼンの文章から資料からすべてを懸命に取り組んでくれてたのよ。」
—— はい。
玉木「それが実ったという意味で、すごく私も嬉しかった。」
—— 広報の藤本さんと映像担当の久保さん、tamaki niimeの発信を担うおふたりが…
玉木「そう。tamaki niimeをわかってもらうために、どのように表現したらいいかということをほんと試行錯誤して、内部にいるんだけど客観的視点に立って、ウチの魅力を伝えようとすごく掘り下げてくれたおかげで、私たちも、そうか!と自分たちを捉え直せたし、tamaki niimeってだんだんと“複雑系”になってるだけに伝えるのが難しいところを上手に伝えてくれたのはすごく嬉しかったです。」
—— スタッフが率先してtamaki niimeというブランドの本質を世に知らしめたい、というところが…
玉木「そう。それがすごく動き出したなって感じる一年だったですね。」
—— スタッフの方たち自らが客観的にtamaki niimeを把握した上で発信を手掛ける機会にもなったというわけですね。
玉木「あ、知ってもらうって、こうゆうことの積み重ねなんだな、って思って。」
—— 「niime村」にもリンクする、自分たちの日々の取り組みをきちんと社会に伝えたい、というところで力を注がれたんだと思うんですけど。
玉木「そういう意味ではやっぱり、色んな人がいて自分ひとりで創ってるんじゃないんだってところをもっとちゃんと伝えたいなと思ってたけど、なかなか叶わなかった頃から比べると、いや~私何にもしなくても勝手に走って行ってるやん…。と思って…」
—— すごいですよね。
玉木「嬉しい嬉しい…。私いつでも遊べる(笑)。」
—— もう自分の遊びのことだけ考えとけると(笑)。
玉木「最初のうちはね、スタッフにイヤイヤさせてる感がどうしてもあったんですよね。私は「してほしい!」と思ってるけど、皆んなの「したい!」にはなってなかったのが、徐々に徐々に、皆んながやりたいことをやった結果、会社が前進してる、という感じにな りつつあるなと。良い流れになって来てるな、と思っています。」
—— そこは玉木社長のビジョンを皆さんが咀嚼して、それぞれに自分の想いや考えを重ね合わせて活動出来るようになって来ているということですかね。
玉木「道のりは一日にしては成らないけれど、以前よりはほんとにああだこうだ言わなくても、勝手にやってくれる人が増えてきてるから、これからも愉しみですね。」
—— はい。
玉木「もちろん私も何か閃いたら言うし、やりたいことがあったらやろうとは思うけど、皆んながそうなって来てるな~、もっともっとそうなってくれたら良いな~って。」
—— 個々の主体的な動きがtamaki niime全体をどんどんと活性化させてゆく、そんな動きが軌道に乗った感がありますね。
玉木「2022年は、西脇のお隣の多可町との取り組みも増えそうよ。工務店さんに伺って、多可町のヒノキスゴイやん!ってなって。「嶋」でヒノキ材を売ろうかと。ついに、「衣・ 食・住」の「住」も、多可町産のヒノキを扱うところから広げられるかもしれない。」
—— 「嶋」でこれから始まる布屋の展開にしても、前回の「niime百科」で宮崎さんも言ってましたけど、ここにはオモシロイ布がたくさんあって宝庫だと。それって、お客様だったり、外部の人にとってもそうだと思うんです。
玉木「そうよ、絶対そう。」
—— この布でこんなの創りたい!という妄想が湧き上がるような…。tamaki niimeの布を、例えば海外のアーティストからの発注を受けて素材として使ってもらうことも考えられますよね。
玉木「布の面白さをアーティストさんに追求してもらったり。織機一台そんなニーズのために空けてますってすれば、こっちに来ていただいて創作どうぞ!って対応も全然可能だし。お互い刺激し合えるから良いような気がするんだけどな。今後そんなことが出来たら 良いかも。」
—— う~ん…ほんとそうですよね…。
玉木「色々やることあるね。2022年も忙しくなるね。愉しみ愉しみ。」
書き人越川誠司