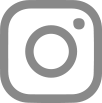niime 百科
Encyclopedia of niime
伊藤先生、ありがとうございました。
<後半>
伊藤先生、ありがとうございました。
<後半>
<後半>
<後半>

2025 . 03 . 14
〈前編からの続き〉
—— 玉木さん、力織機を入れてからどれくらいで織れ始めたんですか?いきなりショールを織ったのではなくて??
玉木「平織りから始まって……あんまりその時の記憶がないんですよ。たぶん3ヶ月くらいで「only one shawl」は出来上がったんじゃないかな。」
—— ふぅぅ~~ん。。。
玉木「機械を動かす練習というよりかは、何を織るかに取り組んだ感じ。」
—— いきなり実践ですね。
玉木「超実践。どんどんどんどん。確かに難しかったけど。」
—— そっちの方が上達も速そうですよね。
玉木「もうやるしかないからね。」
—— 創りたいモノを創ってゆく。
玉木「伊藤先生に夜中に電話して、いきなり糸切れたんやけど、なんで?、とか(笑)。それはさすがに明日でええか? …わかりました!って。」
—— (笑)。
玉木「でも、力織機ですごくよかったなって思うのは…見てわかるんですよ、どこが悪いのかが。その後のレピア織機とかジャカード織機だと、電子的な部品がいっぱい付く感じなんですよ。だから、動きを追えないの。でも力織機って全部のパーツが鉄で、鉄の塊だから。このボタンを押したらここが作動してさらにこっちが動いて…って、様子を観てたら全部わかるの。どう動かしたいかは機械に訊けた。」
—— はい。
玉木「だから、自分が動かしたいように動かすにはを、織機と対話出来るというオモシロさがあって…それが楽しかったの。」
—— こうしたらこうなるという動きが手に取るようにわかると。
玉木「パーツが壊れて伊藤先生に頼んで直してもらって、というのも散々やったんですよ。乱暴だったのか、私の使い方が悪かったんだろうとは思うけど(笑)、そこを、伊藤先生と二人三脚で進んで行けたから、あの力織機で、他所にはない唯一無二だと思える、一生創り続けたいというショールを創ることが出来たから…それは伊藤先生のおかげですよ。」
—— 力織機を手に入れた当初からカスタム化していったところはあるんですか?
玉木「力織機自体はまんま使ってます。あるモノを活かすというスタンスでしか、やりたくないな、と思った。」
—— そのまんまの織機のポテンシャルを引き出すと。
玉木「特に、大柄にしたい人なので、私は。細かい柄は嫌だから、横の柄を出すってゆうのに一番苦戦した。生地の組織ももちろんだけど、柔らかい風合いにどうやってするか?ってゆうのを、元々備わっていた力織機のパーツを駆使して、最大限柔らかい織り方を模索して。横糸の柄の作り方にしても、その鉄板みたいなパーツの種類が限られているのよ。だから無限には柄を創れない。今手元にある鉄板を使って、最大限長くてリピートのない柄をどうやって創るのか?の3ヶ月だった。」
—— 力織機のポテンシャルを自分が望むように最大限引き出すような試行錯誤だったという。
玉木「色もね。再現性の無い柄になるように、どう出来るか?ってゆうのは…いわば、この力織機を使った、誰もが出来ないことを私がやるのにはどうしたら良いか?をずっと考えてた。」
—— なんというか…唯一無二というところの…
玉木「私でしか出来ないモノでないと、わざわざ織機を導入した意味もないし、西脇でこれをやる意味もないから、そこへの追求だけは妥協したらアカンなと思って3ヶ月間やり続けました。」
—— その場に伊藤先生が毎日のようにいらしたと。
玉木「しょっちゅう付き合ってもらった。ヘンな音する!シャトルが飛び出る!っとか。そんなんばっかり(笑)。」
—— はぁ~。。
玉木「感覚的に使ってるから不具合の理由はわからないんですよ…。力織機とはなんぞや?、という理屈も勉強してないし。皆さん学校とかでちゃんと学んだ上でやってるわけですけど、テキトーに動かしてたらあれ?シャトルが飛び出すな、オカシイなと(笑)。その度に伊藤先生が直してくれた。」
—— 古い織機なのでマニュアルも説明書もないわけですよね。とりあえず実践でやってみて…
玉木「とりあえず動かしてみた。簡単な構造原理は聞いたけど…経糸が手前にやってきて、緯糸がポンポン飛ぶから機が織れて行くんだ、と。だけどやっぱり私がやっていたのはあくまでも研究とデザインだったから。機械のメンテナンスに関しては、本当に伊藤先生にドップリだった。経験が無いしなぜ動かないのかわからないから、常に伊藤先生を呼んで訊くってゆう日々を延々続けてましたね。…だから、いてくれなかったら、織れなかったと思う。」
—— そもそも、そんなアプローチをするデザイナーっていなかったでしょうね。
玉木「たぶんね…。いなかったと思うよ。」
自らの手で織機を操り生地の感触を確かめ、試行錯誤し研究を重ねながら想いのままに創作を繰り広げる。
玉木の体当たりなモノづくりの方法論は、彼女ならではの、前例なき、唯一無二のものだったと言えるだろう。
—— “空前絶後”というか…。播州織に限らず、かつての工場での女子従業員の方々の役割にしても決められた通りのやり方で…
玉木「指示書通りにいかに織るかだからね。」
—— そうじゃなくて、やってみたいからやってるという…
玉木「触らせて!って言って。」
—— 伊藤先生はそれを面白がって…
玉木「うん。一緒にやってくれた…。」
—— 二人三脚でやってくださったという。
玉木「もう嫌や、って怒られたことはない。」
—— 改めてそう考えると、tamaki niime の歴史の中でも…
玉木「重要人物。だって、これまで織るメンバーはかなり変わって来てるわけですよ。私から始まって、代々色んなスタッフが携わって来たにも関わらず、伊藤先生はずっといてくれたから。ホントに私にとっては「織チーム」の柱みたいな存在だった。」
—— はい。
玉木「だから私にとっては伊藤先生がいなくなったことってすごくダメージが大きくて。あぁ……ってなるじゃないですか?もういざという時にメンテナンスしてもらえる人がいないってことだから…。」
—— 掛け替えのない存在…
玉木「もちろんお元気な間にちゃんと引き継ぎなさいとは言って来たよ。だから、これからウチのスタッフがどれだけ教えを受け継いでいるかが実際に見えてくる。活躍していってくれるとは信じてるけど、伊藤先生みたいに出来るかどうかはまだわからないよね。」
—— …。
玉木「西角さんとかにも助けてほしいとお願いして。でもその時に言われたのは、俺は教えへんど、と。まずは説明書を読め、と。力織機にはないけどレピア織機ならあるから。まずは読んで自分で理解しようとして、その上で使ってみてわからないことに関しては、訊いたら答えてやる、と。でも座ってたら先生が教えてくれるというもんやないど、と。おっしゃる通りですと。その意思を持って、皆んなが「織」を出来るか?今までは先生、先生と、伊藤先生を呼んだら助けてもらえたから。何か機械がおかしいんです、うまく織れないんです、って頼ったら…のび太にとってのドラえもんみたいな存在だったわけじゃないですか?」
—— 答えがポンっと、ドラえもんのポケットならぬ、伊藤先生の技術の引き出しから出てくるみたいな…。
玉木「そう。ここが問題だよ、って教えてくれて、しかも直してもくれる人だったのが…ドラえもんがいなくなったのび太ってやばいじゃないですか?(笑)」
—— 自力でなんとかしないと、という。
玉木「そう。だから“緊急事態宣言”を出して、茶谷と藤本、かつての「織チーム」のスタッフ2人も復帰させた。2人とも伊藤先生から引き継いでいるものがあるだろうと。他の業務もあるけれど、メンテナンスも含めて、谷口君と九後さんだけでは大変だから、一緒にやっていってほしいと。体制を変えました。」
—— 伊藤先生のお弟子さんが結集して。
玉木「もう自分たちでやって行けってことだから、ちゃんとしなければいけないなと思って。…ここ1、2年で伊藤先生もそうだけど、初子さんでしょ、國男さんでしょ…やっぱり、背中で見せて来てくれた私たちの親的存在がいなくなって、やるべきことを自分でやれ、と。私たちの世代がちゃんとやって、下の世代に見せていかなきゃいけない、というバトンを受け取るタイミングなのだろうなぁと。」
—— 色んなtamaki niimeからの頼まれ事が伊藤先生にとっては嬉しかったんでしょうし、大きな意味でいえば、播州織というこの地域の文化を若い世代に引き継いでもらえているという実感があったんだと思います。
玉木「家族の人たちを連れてきてくれてたらしくて。lab案内して、織機を動かして。カッコつけて見せびらかしてたそうだから(笑)、自慢ではあったんだろうね。」
—— 誇らしげに…。
玉木「色んな処に出かけてはウチを宣伝してくれたり、逆に今治にある「タオル美術館」という、タオルの製造工程が一度に観れるミュージアムがあるんですけど、無茶エエから行って来たらいいぞ、って教えてくれたり、谷口君を一緒に連れてってくれたりだとか。」
—— 人脈を活かした広報活動も。メンテナンスの技術者に留まらずに…
玉木「そう。違うねん。色んな人を連れてきてくれたりだとか…。」
—— それもまた人づてのご縁ですよね。
玉木「そう。ホントに伊藤先生はじめ、そんな方々に囲まれていたからこそ、今まで続けて来られたんだな、って思いました。西脇でモノづくりを始めた当時はSNSをガッツリやってたわけじゃないし、色んな人が人を連れてきてくださって、またその人が人を連れてきてくださって…ずっとその連鎖だから。これからも、このshop&labが、わざわざ連れて来たいと思ってもらえるような場所であり続けないとそれは成し得ないと思うし…。」
—— …。
玉木「…伊藤先生、面白がってくれたんだろうね?」
—— ……お話を聞いて、やっぱり良い意味で“クレイジー”な人だったんでしょうね。「589」から「上野」のshop&labへ、そして今やそれこそミュージアムみたいに色々な織機が並んでいるここへの移動なんかも伊藤先生が?
玉木「伊藤先生が陣頭指揮をとって何人かのチームプレーでガーンと動かしてもらって、やってくれました。どんどん伊藤先生みたいに機械を熟知されている人が少なくなってゆくのと、たまたま土田さんとの出会いがあって、この力織機に巡りあって、岩間織機制作所というメーカーの機械なんですけど、これは播州織産地の中ではレアな織機らしいんですよ。やっぱりメーカーによって機械の構造やパーツが異なるから、伊藤先生が要で。その存在がいなくなった後、どう補っていくかは手探りでやって行くしかない、頑張ろう、って感じですね。」
—— 伊藤先生のメンテナンス力、技術力というのも、替えのきかない、“唯一無二”というか。
玉木「いやホント、誰もいないですね。機料店さんに訊いても、伊藤先生の替わりになるような人は?…おらん、他の産地には?…おらん、って。だから他にも伊藤先生を頼りにしていた高齢の機屋さんたちもどうしよう?って言って、困っている。だって84歳で現役だったってことは、よっぽど誰もおらんって事でしょ?」
—— 昔の力織機まで扱える人ってなったら本当に限られてくるって話ですね。
玉木「まずいないんですよ、力織機を扱える人が。世代的に力織機の経験があるのは西角さんの世代、70代後半くらいまでだね。」
—— そうなんですね…。
玉木「まぁ力織機は最悪の場合、稼働を終えて飾ることにするとしても、レピア織機やしっかり動いてる織機はずっと使っていきたいし、最後に伊藤先生が良い機械をと、ジャカード織の織機を新たに入れてくれたのが整備途中なので…先生としてはやり残した感が一杯で、早くtamaki niimeに行かな、ってずっと言ってたって。」
—— それはお亡くなりになる前に?
玉木「しばらく休んでいて、ウチに久しぶりに来た日があったんです。そこで私も話が出来て。だいじょうぶ~!??って言って。「もう、はよtamaki niimeに行ってメンテやらな、行きたくてしゃあなかった。」って。だから、「引き戻されたね…。」って話してたの。」
—— 最後まで、tamaki niimeの織機たちを気にして…
玉木「これからまだ正念場ですよ、私たちの。織を続けられるのか?まあ、伊藤先生が見守ってくれてるとは思います。残された若者たちの力量が試されている2025年ですね。」
—— そこは伊藤先生のお弟子さんたちが。
玉木「やるしかない。乞うご期待!って感じです。」
“愛弟子”と呼べる谷口希望にもこの場に来てもらい、「伊藤先生」を語ってもらった。
谷口「本当に、公私ともに無茶苦茶お世話になっていたので、もう、これからどうしよう…?ではあるんですけど、出来るように、やるしかねぇわ!と。まだまだ教えてもらい足りなかったんですけど、受け取ったものを絶対に無駄にしないように、頑張りたいと思っています。」
—— 公私ともに。
玉木「だって、家にも織機置いてるからさぁ。それも岩間のなの?」
谷口「岩間のやや小さめの。」
玉木「そうなの?伊藤先生の跡取りは谷口君や。岩間のことならオレに聞け、と(笑)。」
谷口「休みの日に日生の方に、よし、牡蠣食いに行くぞ~!」って遊びに行かせてもらったりもしました…。」
—— 伊藤先生の遺されたジャカードの織機をただ今メンテナンス中だとか?
谷口「はい。」
玉木「たぶんすぐ隣で見てくれてるよ。あとは皆んなが頑張ってくれますから、愉しみにしましょ!」
最後は酒井に締めてもらおう。
酒井「伊藤先生は、もう亡くなられたけど、播州織産地に残っていた最後の天才であり異端児だったと思います。常に新しいことにチャレンジしようとする人で、良い意味で前のめりだった人なんで。」
—— エネルギッシュな人だったと聞きました。ずっと動いてる人だったと。
酒井「そうなんスよ。だから、稀有な人っていうか。いなくなってみないとその偉大さがわからない。残された僕たちがどう引き継いで行くか?伊藤先生は「走る人」。最後まで走ってた人でした。」
織機の音が響く「織」の現場はtamaki niimeのモノづくりの心臓部だ。
そこは、播州織の歴史とともに歩んだひとりの型破りな機械職人が、終の住処にするように、己れの生命を燃焼させた場所でもあった。
留まらず最後まで疾走を続けた伊藤義忠さん。「伊藤先生を偲ぶ会」は1月16日(木)の夜、tamaki niime tabe roomにて、長年故人と関わって来た産地の人たちも集まり行われた。
会場に設られた大型モニターには、スタッフとともに織機と戯れる「伊藤先生」の笑顔が繰り返し繰り返し映し出されていた。
—— 玉木さん、力織機を入れてからどれくらいで織れ始めたんですか?いきなりショールを織ったのではなくて??
玉木「平織りから始まって……あんまりその時の記憶がないんですよ。たぶん3ヶ月くらいで「only one shawl」は出来上がったんじゃないかな。」
—— ふぅぅ~~ん。。。
玉木「機械を動かす練習というよりかは、何を織るかに取り組んだ感じ。」
—— いきなり実践ですね。
玉木「超実践。どんどんどんどん。確かに難しかったけど。」
—— そっちの方が上達も速そうですよね。
玉木「もうやるしかないからね。」
—— 創りたいモノを創ってゆく。
玉木「伊藤先生に夜中に電話して、いきなり糸切れたんやけど、なんで?、とか(笑)。それはさすがに明日でええか? …わかりました!って。」
—— (笑)。
玉木「でも、力織機ですごくよかったなって思うのは…見てわかるんですよ、どこが悪いのかが。その後のレピア織機とかジャカード織機だと、電子的な部品がいっぱい付く感じなんですよ。だから、動きを追えないの。でも力織機って全部のパーツが鉄で、鉄の塊だから。このボタンを押したらここが作動してさらにこっちが動いて…って、様子を観てたら全部わかるの。どう動かしたいかは機械に訊けた。」
—— はい。
玉木「だから、自分が動かしたいように動かすにはを、織機と対話出来るというオモシロさがあって…それが楽しかったの。」
—— こうしたらこうなるという動きが手に取るようにわかると。
玉木「パーツが壊れて伊藤先生に頼んで直してもらって、というのも散々やったんですよ。乱暴だったのか、私の使い方が悪かったんだろうとは思うけど(笑)、そこを、伊藤先生と二人三脚で進んで行けたから、あの力織機で、他所にはない唯一無二だと思える、一生創り続けたいというショールを創ることが出来たから…それは伊藤先生のおかげですよ。」
—— 力織機を手に入れた当初からカスタム化していったところはあるんですか?
玉木「力織機自体はまんま使ってます。あるモノを活かすというスタンスでしか、やりたくないな、と思った。」
—— そのまんまの織機のポテンシャルを引き出すと。
玉木「特に、大柄にしたい人なので、私は。細かい柄は嫌だから、横の柄を出すってゆうのに一番苦戦した。生地の組織ももちろんだけど、柔らかい風合いにどうやってするか?ってゆうのを、元々備わっていた力織機のパーツを駆使して、最大限柔らかい織り方を模索して。横糸の柄の作り方にしても、その鉄板みたいなパーツの種類が限られているのよ。だから無限には柄を創れない。今手元にある鉄板を使って、最大限長くてリピートのない柄をどうやって創るのか?の3ヶ月だった。」
—— 力織機のポテンシャルを自分が望むように最大限引き出すような試行錯誤だったという。
玉木「色もね。再現性の無い柄になるように、どう出来るか?ってゆうのは…いわば、この力織機を使った、誰もが出来ないことを私がやるのにはどうしたら良いか?をずっと考えてた。」
—— なんというか…唯一無二というところの…
玉木「私でしか出来ないモノでないと、わざわざ織機を導入した意味もないし、西脇でこれをやる意味もないから、そこへの追求だけは妥協したらアカンなと思って3ヶ月間やり続けました。」
—— その場に伊藤先生が毎日のようにいらしたと。
玉木「しょっちゅう付き合ってもらった。ヘンな音する!シャトルが飛び出る!っとか。そんなんばっかり(笑)。」
—— はぁ~。。
玉木「感覚的に使ってるから不具合の理由はわからないんですよ…。力織機とはなんぞや?、という理屈も勉強してないし。皆さん学校とかでちゃんと学んだ上でやってるわけですけど、テキトーに動かしてたらあれ?シャトルが飛び出すな、オカシイなと(笑)。その度に伊藤先生が直してくれた。」
—— 古い織機なのでマニュアルも説明書もないわけですよね。とりあえず実践でやってみて…
玉木「とりあえず動かしてみた。簡単な構造原理は聞いたけど…経糸が手前にやってきて、緯糸がポンポン飛ぶから機が織れて行くんだ、と。だけどやっぱり私がやっていたのはあくまでも研究とデザインだったから。機械のメンテナンスに関しては、本当に伊藤先生にドップリだった。経験が無いしなぜ動かないのかわからないから、常に伊藤先生を呼んで訊くってゆう日々を延々続けてましたね。…だから、いてくれなかったら、織れなかったと思う。」
—— そもそも、そんなアプローチをするデザイナーっていなかったでしょうね。
玉木「たぶんね…。いなかったと思うよ。」
自らの手で織機を操り生地の感触を確かめ、試行錯誤し研究を重ねながら想いのままに創作を繰り広げる。
玉木の体当たりなモノづくりの方法論は、彼女ならではの、前例なき、唯一無二のものだったと言えるだろう。
—— “空前絶後”というか…。播州織に限らず、かつての工場での女子従業員の方々の役割にしても決められた通りのやり方で…
玉木「指示書通りにいかに織るかだからね。」
—— そうじゃなくて、やってみたいからやってるという…
玉木「触らせて!って言って。」
—— 伊藤先生はそれを面白がって…
玉木「うん。一緒にやってくれた…。」
—— 二人三脚でやってくださったという。
玉木「もう嫌や、って怒られたことはない。」
—— 改めてそう考えると、tamaki niime の歴史の中でも…
玉木「重要人物。だって、これまで織るメンバーはかなり変わって来てるわけですよ。私から始まって、代々色んなスタッフが携わって来たにも関わらず、伊藤先生はずっといてくれたから。ホントに私にとっては「織チーム」の柱みたいな存在だった。」
—— はい。
玉木「だから私にとっては伊藤先生がいなくなったことってすごくダメージが大きくて。あぁ……ってなるじゃないですか?もういざという時にメンテナンスしてもらえる人がいないってことだから…。」
—— 掛け替えのない存在…
玉木「もちろんお元気な間にちゃんと引き継ぎなさいとは言って来たよ。だから、これからウチのスタッフがどれだけ教えを受け継いでいるかが実際に見えてくる。活躍していってくれるとは信じてるけど、伊藤先生みたいに出来るかどうかはまだわからないよね。」
—— …。
玉木「西角さんとかにも助けてほしいとお願いして。でもその時に言われたのは、俺は教えへんど、と。まずは説明書を読め、と。力織機にはないけどレピア織機ならあるから。まずは読んで自分で理解しようとして、その上で使ってみてわからないことに関しては、訊いたら答えてやる、と。でも座ってたら先生が教えてくれるというもんやないど、と。おっしゃる通りですと。その意思を持って、皆んなが「織」を出来るか?今までは先生、先生と、伊藤先生を呼んだら助けてもらえたから。何か機械がおかしいんです、うまく織れないんです、って頼ったら…のび太にとってのドラえもんみたいな存在だったわけじゃないですか?」
—— 答えがポンっと、ドラえもんのポケットならぬ、伊藤先生の技術の引き出しから出てくるみたいな…。
玉木「そう。ここが問題だよ、って教えてくれて、しかも直してもくれる人だったのが…ドラえもんがいなくなったのび太ってやばいじゃないですか?(笑)」
—— 自力でなんとかしないと、という。
玉木「そう。だから“緊急事態宣言”を出して、茶谷と藤本、かつての「織チーム」のスタッフ2人も復帰させた。2人とも伊藤先生から引き継いでいるものがあるだろうと。他の業務もあるけれど、メンテナンスも含めて、谷口君と九後さんだけでは大変だから、一緒にやっていってほしいと。体制を変えました。」
—— 伊藤先生のお弟子さんが結集して。
玉木「もう自分たちでやって行けってことだから、ちゃんとしなければいけないなと思って。…ここ1、2年で伊藤先生もそうだけど、初子さんでしょ、國男さんでしょ…やっぱり、背中で見せて来てくれた私たちの親的存在がいなくなって、やるべきことを自分でやれ、と。私たちの世代がちゃんとやって、下の世代に見せていかなきゃいけない、というバトンを受け取るタイミングなのだろうなぁと。」
—— 色んなtamaki niimeからの頼まれ事が伊藤先生にとっては嬉しかったんでしょうし、大きな意味でいえば、播州織というこの地域の文化を若い世代に引き継いでもらえているという実感があったんだと思います。
玉木「家族の人たちを連れてきてくれてたらしくて。lab案内して、織機を動かして。カッコつけて見せびらかしてたそうだから(笑)、自慢ではあったんだろうね。」
—— 誇らしげに…。
玉木「色んな処に出かけてはウチを宣伝してくれたり、逆に今治にある「タオル美術館」という、タオルの製造工程が一度に観れるミュージアムがあるんですけど、無茶エエから行って来たらいいぞ、って教えてくれたり、谷口君を一緒に連れてってくれたりだとか。」
—— 人脈を活かした広報活動も。メンテナンスの技術者に留まらずに…
玉木「そう。違うねん。色んな人を連れてきてくれたりだとか…。」
—— それもまた人づてのご縁ですよね。
玉木「そう。ホントに伊藤先生はじめ、そんな方々に囲まれていたからこそ、今まで続けて来られたんだな、って思いました。西脇でモノづくりを始めた当時はSNSをガッツリやってたわけじゃないし、色んな人が人を連れてきてくださって、またその人が人を連れてきてくださって…ずっとその連鎖だから。これからも、このshop&labが、わざわざ連れて来たいと思ってもらえるような場所であり続けないとそれは成し得ないと思うし…。」
—— …。
玉木「…伊藤先生、面白がってくれたんだろうね?」
—— ……お話を聞いて、やっぱり良い意味で“クレイジー”な人だったんでしょうね。「589」から「上野」のshop&labへ、そして今やそれこそミュージアムみたいに色々な織機が並んでいるここへの移動なんかも伊藤先生が?
玉木「伊藤先生が陣頭指揮をとって何人かのチームプレーでガーンと動かしてもらって、やってくれました。どんどん伊藤先生みたいに機械を熟知されている人が少なくなってゆくのと、たまたま土田さんとの出会いがあって、この力織機に巡りあって、岩間織機制作所というメーカーの機械なんですけど、これは播州織産地の中ではレアな織機らしいんですよ。やっぱりメーカーによって機械の構造やパーツが異なるから、伊藤先生が要で。その存在がいなくなった後、どう補っていくかは手探りでやって行くしかない、頑張ろう、って感じですね。」
—— 伊藤先生のメンテナンス力、技術力というのも、替えのきかない、“唯一無二”というか。
玉木「いやホント、誰もいないですね。機料店さんに訊いても、伊藤先生の替わりになるような人は?…おらん、他の産地には?…おらん、って。だから他にも伊藤先生を頼りにしていた高齢の機屋さんたちもどうしよう?って言って、困っている。だって84歳で現役だったってことは、よっぽど誰もおらんって事でしょ?」
—— 昔の力織機まで扱える人ってなったら本当に限られてくるって話ですね。
玉木「まずいないんですよ、力織機を扱える人が。世代的に力織機の経験があるのは西角さんの世代、70代後半くらいまでだね。」
—— そうなんですね…。
玉木「まぁ力織機は最悪の場合、稼働を終えて飾ることにするとしても、レピア織機やしっかり動いてる織機はずっと使っていきたいし、最後に伊藤先生が良い機械をと、ジャカード織の織機を新たに入れてくれたのが整備途中なので…先生としてはやり残した感が一杯で、早くtamaki niimeに行かな、ってずっと言ってたって。」
—— それはお亡くなりになる前に?
玉木「しばらく休んでいて、ウチに久しぶりに来た日があったんです。そこで私も話が出来て。だいじょうぶ~!??って言って。「もう、はよtamaki niimeに行ってメンテやらな、行きたくてしゃあなかった。」って。だから、「引き戻されたね…。」って話してたの。」
—— 最後まで、tamaki niimeの織機たちを気にして…
玉木「これからまだ正念場ですよ、私たちの。織を続けられるのか?まあ、伊藤先生が見守ってくれてるとは思います。残された若者たちの力量が試されている2025年ですね。」
—— そこは伊藤先生のお弟子さんたちが。
玉木「やるしかない。乞うご期待!って感じです。」
“愛弟子”と呼べる谷口希望にもこの場に来てもらい、「伊藤先生」を語ってもらった。
谷口「本当に、公私ともに無茶苦茶お世話になっていたので、もう、これからどうしよう…?ではあるんですけど、出来るように、やるしかねぇわ!と。まだまだ教えてもらい足りなかったんですけど、受け取ったものを絶対に無駄にしないように、頑張りたいと思っています。」
—— 公私ともに。
玉木「だって、家にも織機置いてるからさぁ。それも岩間のなの?」
谷口「岩間のやや小さめの。」
玉木「そうなの?伊藤先生の跡取りは谷口君や。岩間のことならオレに聞け、と(笑)。」
谷口「休みの日に日生の方に、よし、牡蠣食いに行くぞ~!」って遊びに行かせてもらったりもしました…。」
—— 伊藤先生の遺されたジャカードの織機をただ今メンテナンス中だとか?
谷口「はい。」
玉木「たぶんすぐ隣で見てくれてるよ。あとは皆んなが頑張ってくれますから、愉しみにしましょ!」
最後は酒井に締めてもらおう。
酒井「伊藤先生は、もう亡くなられたけど、播州織産地に残っていた最後の天才であり異端児だったと思います。常に新しいことにチャレンジしようとする人で、良い意味で前のめりだった人なんで。」
—— エネルギッシュな人だったと聞きました。ずっと動いてる人だったと。
酒井「そうなんスよ。だから、稀有な人っていうか。いなくなってみないとその偉大さがわからない。残された僕たちがどう引き継いで行くか?伊藤先生は「走る人」。最後まで走ってた人でした。」
織機の音が響く「織」の現場はtamaki niimeのモノづくりの心臓部だ。
そこは、播州織の歴史とともに歩んだひとりの型破りな機械職人が、終の住処にするように、己れの生命を燃焼させた場所でもあった。
留まらず最後まで疾走を続けた伊藤義忠さん。「伊藤先生を偲ぶ会」は1月16日(木)の夜、tamaki niime tabe roomにて、長年故人と関わって来た産地の人たちも集まり行われた。
会場に設られた大型モニターには、スタッフとともに織機と戯れる「伊藤先生」の笑顔が繰り返し繰り返し映し出されていた。
書き人越川誠司
〈前編からの続き〉
—— 玉木さん、力織機を入れてからどれくらいで織れ始めたんですか?いきなりショールを織ったのではなくて??
玉木「平織りから始まって……あんまりその時の記憶がないんですよ。たぶん3ヶ月くらいで「only one shawl」は出来上がったんじゃないかな。」
—— ふぅぅ~~ん。。。
玉木「機械を動かす練習というよりかは、何を織るかに取り組んだ感じ。」
—— いきなり実践ですね。
玉木「超実践。どんどんどんどん。確かに難しかったけど。」
—— そっちの方が上達も速そうですよね。
玉木「もうやるしかないからね。」
—— 創りたいモノを創ってゆく。
玉木「伊藤先生に夜中に電話して、いきなり糸切れたんやけど、なんで?、とか(笑)。それはさすがに明日でええか? …わかりました!って。」
—— (笑)。
玉木「でも、力織機ですごくよかったなって思うのは…見てわかるんですよ、どこが悪いのかが。その後のレピア織機とかジャカード織機だと、電子的な部品がいっぱい付く感じなんですよ。だから、動きを追えないの。でも力織機って全部のパーツが鉄で、鉄の塊だから。このボタンを押したらここが作動してさらにこっちが動いて…って、様子を観てたら全部わかるの。どう動かしたいかは機械に訊けた。」
—— はい。
玉木「だから、自分が動かしたいように動かすにはを、織機と対話出来るというオモシロさがあって…それが楽しかったの。」
—— こうしたらこうなるという動きが手に取るようにわかると。
玉木「パーツが壊れて伊藤先生に頼んで直してもらって、というのも散々やったんですよ。乱暴だったのか、私の使い方が悪かったんだろうとは思うけど(笑)、そこを、伊藤先生と二人三脚で進んで行けたから、あの力織機で、他所にはない唯一無二だと思える、一生創り続けたいというショールを創ることが出来たから…それは伊藤先生のおかげですよ。」
—— 力織機を手に入れた当初からカスタム化していったところはあるんですか?
玉木「力織機自体はまんま使ってます。あるモノを活かすというスタンスでしか、やりたくないな、と思った。」
—— そのまんまの織機のポテンシャルを引き出すと。
玉木「特に、大柄にしたい人なので、私は。細かい柄は嫌だから、横の柄を出すってゆうのに一番苦戦した。生地の組織ももちろんだけど、柔らかい風合いにどうやってするか?ってゆうのを、元々備わっていた力織機のパーツを駆使して、最大限柔らかい織り方を模索して。横糸の柄の作り方にしても、その鉄板みたいなパーツの種類が限られているのよ。だから無限には柄を創れない。今手元にある鉄板を使って、最大限長くてリピートのない柄をどうやって創るのか?の3ヶ月だった。」
—— 力織機のポテンシャルを自分が望むように最大限引き出すような試行錯誤だったという。
玉木「色もね。再現性の無い柄になるように、どう出来るか?ってゆうのは…いわば、この力織機を使った、誰もが出来ないことを私がやるのにはどうしたら良いか?をずっと考えてた。」
—— なんというか…唯一無二というところの…
玉木「私でしか出来ないモノでないと、わざわざ織機を導入した意味もないし、西脇でこれをやる意味もないから、そこへの追求だけは妥協したらアカンなと思って3ヶ月間やり続けました。」
—— その場に伊藤先生が毎日のようにいらしたと。
玉木「しょっちゅう付き合ってもらった。ヘンな音する!シャトルが飛び出る!っとか。そんなんばっかり(笑)。」
—— はぁ~。。
玉木「感覚的に使ってるから不具合の理由はわからないんですよ…。力織機とはなんぞや?、という理屈も勉強してないし。皆さん学校とかでちゃんと学んだ上でやってるわけですけど、テキトーに動かしてたらあれ?シャトルが飛び出すな、オカシイなと(笑)。その度に伊藤先生が直してくれた。」
—— 古い織機なのでマニュアルも説明書もないわけですよね。とりあえず実践でやってみて…
玉木「とりあえず動かしてみた。簡単な構造原理は聞いたけど…経糸が手前にやってきて、緯糸がポンポン飛ぶから機が織れて行くんだ、と。だけどやっぱり私がやっていたのはあくまでも研究とデザインだったから。機械のメンテナンスに関しては、本当に伊藤先生にドップリだった。経験が無いしなぜ動かないのかわからないから、常に伊藤先生を呼んで訊くってゆう日々を延々続けてましたね。…だから、いてくれなかったら、織れなかったと思う。」
—— そもそも、そんなアプローチをするデザイナーっていなかったでしょうね。
玉木「たぶんね…。いなかったと思うよ。」
自らの手で織機を操り生地の感触を確かめ、試行錯誤し研究を重ねながら想いのままに創作を繰り広げる。
玉木の体当たりなモノづくりの方法論は、彼女ならではの、前例なき、唯一無二のものだったと言えるだろう。
—— “空前絶後”というか…。播州織に限らず、かつての工場での女子従業員の方々の役割にしても決められた通りのやり方で…
玉木「指示書通りにいかに織るかだからね。」
—— そうじゃなくて、やってみたいからやってるという…
玉木「触らせて!って言って。」
—— 伊藤先生はそれを面白がって…
玉木「うん。一緒にやってくれた…。」
—— 二人三脚でやってくださったという。
玉木「もう嫌や、って怒られたことはない。」
—— 改めてそう考えると、tamaki niime の歴史の中でも…
玉木「重要人物。だって、これまで織るメンバーはかなり変わって来てるわけですよ。私から始まって、代々色んなスタッフが携わって来たにも関わらず、伊藤先生はずっといてくれたから。ホントに私にとっては「織チーム」の柱みたいな存在だった。」
—— はい。
玉木「だから私にとっては伊藤先生がいなくなったことってすごくダメージが大きくて。あぁ……ってなるじゃないですか?もういざという時にメンテナンスしてもらえる人がいないってことだから…。」
—— 掛け替えのない存在…
玉木「もちろんお元気な間にちゃんと引き継ぎなさいとは言って来たよ。だから、これからウチのスタッフがどれだけ教えを受け継いでいるかが実際に見えてくる。活躍していってくれるとは信じてるけど、伊藤先生みたいに出来るかどうかはまだわからないよね。」
—— …。
玉木「西角さんとかにも助けてほしいとお願いして。でもその時に言われたのは、俺は教えへんど、と。まずは説明書を読め、と。力織機にはないけどレピア織機ならあるから。まずは読んで自分で理解しようとして、その上で使ってみてわからないことに関しては、訊いたら答えてやる、と。でも座ってたら先生が教えてくれるというもんやないど、と。おっしゃる通りですと。その意思を持って、皆んなが「織」を出来るか?今までは先生、先生と、伊藤先生を呼んだら助けてもらえたから。何か機械がおかしいんです、うまく織れないんです、って頼ったら…のび太にとってのドラえもんみたいな存在だったわけじゃないですか?」
—— 答えがポンっと、ドラえもんのポケットならぬ、伊藤先生の技術の引き出しから出てくるみたいな…。
玉木「そう。ここが問題だよ、って教えてくれて、しかも直してもくれる人だったのが…ドラえもんがいなくなったのび太ってやばいじゃないですか?(笑)」
—— 自力でなんとかしないと、という。
玉木「そう。だから“緊急事態宣言”を出して、茶谷と藤本、かつての「織チーム」のスタッフ2人も復帰させた。2人とも伊藤先生から引き継いでいるものがあるだろうと。他の業務もあるけれど、メンテナンスも含めて、谷口君と九後さんだけでは大変だから、一緒にやっていってほしいと。体制を変えました。」
—— 伊藤先生のお弟子さんが結集して。
玉木「もう自分たちでやって行けってことだから、ちゃんとしなければいけないなと思って。…ここ1、2年で伊藤先生もそうだけど、初子さんでしょ、國男さんでしょ…やっぱり、背中で見せて来てくれた私たちの親的存在がいなくなって、やるべきことを自分でやれ、と。私たちの世代がちゃんとやって、下の世代に見せていかなきゃいけない、というバトンを受け取るタイミングなのだろうなぁと。」
—— 色んなtamaki niimeからの頼まれ事が伊藤先生にとっては嬉しかったんでしょうし、大きな意味でいえば、播州織というこの地域の文化を若い世代に引き継いでもらえているという実感があったんだと思います。
玉木「家族の人たちを連れてきてくれてたらしくて。lab案内して、織機を動かして。カッコつけて見せびらかしてたそうだから(笑)、自慢ではあったんだろうね。」
—— 誇らしげに…。
玉木「色んな処に出かけてはウチを宣伝してくれたり、逆に今治にある「タオル美術館」という、タオルの製造工程が一度に観れるミュージアムがあるんですけど、無茶エエから行って来たらいいぞ、って教えてくれたり、谷口君を一緒に連れてってくれたりだとか。」
—— 人脈を活かした広報活動も。メンテナンスの技術者に留まらずに…
玉木「そう。違うねん。色んな人を連れてきてくれたりだとか…。」
—— それもまた人づてのご縁ですよね。
玉木「そう。ホントに伊藤先生はじめ、そんな方々に囲まれていたからこそ、今まで続けて来られたんだな、って思いました。西脇でモノづくりを始めた当時はSNSをガッツリやってたわけじゃないし、色んな人が人を連れてきてくださって、またその人が人を連れてきてくださって…ずっとその連鎖だから。これからも、このshop&labが、わざわざ連れて来たいと思ってもらえるような場所であり続けないとそれは成し得ないと思うし…。」
—— …。
玉木「…伊藤先生、面白がってくれたんだろうね?」
—— ……お話を聞いて、やっぱり良い意味で“クレイジー”な人だったんでしょうね。「589」から「上野」のshop&labへ、そして今やそれこそミュージアムみたいに色々な織機が並んでいるここへの移動なんかも伊藤先生が?
玉木「伊藤先生が陣頭指揮をとって何人かのチームプレーでガーンと動かしてもらって、やってくれました。どんどん伊藤先生みたいに機械を熟知されている人が少なくなってゆくのと、たまたま土田さんとの出会いがあって、この力織機に巡りあって、岩間織機制作所というメーカーの機械なんですけど、これは播州織産地の中ではレアな織機らしいんですよ。やっぱりメーカーによって機械の構造やパーツが異なるから、伊藤先生が要で。その存在がいなくなった後、どう補っていくかは手探りでやって行くしかない、頑張ろう、って感じですね。」
—— 伊藤先生のメンテナンス力、技術力というのも、替えのきかない、“唯一無二”というか。
玉木「いやホント、誰もいないですね。機料店さんに訊いても、伊藤先生の替わりになるような人は?…おらん、他の産地には?…おらん、って。だから他にも伊藤先生を頼りにしていた高齢の機屋さんたちもどうしよう?って言って、困っている。だって84歳で現役だったってことは、よっぽど誰もおらんって事でしょ?」
—— 昔の力織機まで扱える人ってなったら本当に限られてくるって話ですね。
玉木「まずいないんですよ、力織機を扱える人が。世代的に力織機の経験があるのは西角さんの世代、70代後半くらいまでだね。」
—— そうなんですね…。
玉木「まぁ力織機は最悪の場合、稼働を終えて飾ることにするとしても、レピア織機やしっかり動いてる織機はずっと使っていきたいし、最後に伊藤先生が良い機械をと、ジャカード織の織機を新たに入れてくれたのが整備途中なので…先生としてはやり残した感が一杯で、早くtamaki niimeに行かな、ってずっと言ってたって。」
—— それはお亡くなりになる前に?
玉木「しばらく休んでいて、ウチに久しぶりに来た日があったんです。そこで私も話が出来て。だいじょうぶ~!??って言って。「もう、はよtamaki niimeに行ってメンテやらな、行きたくてしゃあなかった。」って。だから、「引き戻されたね…。」って話してたの。」
—— 最後まで、tamaki niimeの織機たちを気にして…
玉木「これからまだ正念場ですよ、私たちの。織を続けられるのか?まあ、伊藤先生が見守ってくれてるとは思います。残された若者たちの力量が試されている2025年ですね。」
—— そこは伊藤先生のお弟子さんたちが。
玉木「やるしかない。乞うご期待!って感じです。」
“愛弟子”と呼べる谷口希望にもこの場に来てもらい、「伊藤先生」を語ってもらった。
谷口「本当に、公私ともに無茶苦茶お世話になっていたので、もう、これからどうしよう…?ではあるんですけど、出来るように、やるしかねぇわ!と。まだまだ教えてもらい足りなかったんですけど、受け取ったものを絶対に無駄にしないように、頑張りたいと思っています。」
—— 公私ともに。
玉木「だって、家にも織機置いてるからさぁ。それも岩間のなの?」
谷口「岩間のやや小さめの。」
玉木「そうなの?伊藤先生の跡取りは谷口君や。岩間のことならオレに聞け、と(笑)。」
谷口「休みの日に日生の方に、よし、牡蠣食いに行くぞ~!」って遊びに行かせてもらったりもしました…。」
—— 伊藤先生の遺されたジャカードの織機をただ今メンテナンス中だとか?
谷口「はい。」
玉木「たぶんすぐ隣で見てくれてるよ。あとは皆んなが頑張ってくれますから、愉しみにしましょ!」
最後は酒井に締めてもらおう。
酒井「伊藤先生は、もう亡くなられたけど、播州織産地に残っていた最後の天才であり異端児だったと思います。常に新しいことにチャレンジしようとする人で、良い意味で前のめりだった人なんで。」
—— エネルギッシュな人だったと聞きました。ずっと動いてる人だったと。
酒井「そうなんスよ。だから、稀有な人っていうか。いなくなってみないとその偉大さがわからない。残された僕たちがどう引き継いで行くか?伊藤先生は「走る人」。最後まで走ってた人でした。」
織機の音が響く「織」の現場はtamaki niimeのモノづくりの心臓部だ。
そこは、播州織の歴史とともに歩んだひとりの型破りな機械職人が、終の住処にするように、己れの生命を燃焼させた場所でもあった。
留まらず最後まで疾走を続けた伊藤義忠さん。「伊藤先生を偲ぶ会」は1月16日(木)の夜、tamaki niime tabe roomにて、長年故人と関わって来た産地の人たちも集まり行われた。
会場に設られた大型モニターには、スタッフとともに織機と戯れる「伊藤先生」の笑顔が繰り返し繰り返し映し出されていた。
—— 玉木さん、力織機を入れてからどれくらいで織れ始めたんですか?いきなりショールを織ったのではなくて??
玉木「平織りから始まって……あんまりその時の記憶がないんですよ。たぶん3ヶ月くらいで「only one shawl」は出来上がったんじゃないかな。」
—— ふぅぅ~~ん。。。
玉木「機械を動かす練習というよりかは、何を織るかに取り組んだ感じ。」
—— いきなり実践ですね。
玉木「超実践。どんどんどんどん。確かに難しかったけど。」
—— そっちの方が上達も速そうですよね。
玉木「もうやるしかないからね。」
—— 創りたいモノを創ってゆく。
玉木「伊藤先生に夜中に電話して、いきなり糸切れたんやけど、なんで?、とか(笑)。それはさすがに明日でええか? …わかりました!って。」
—— (笑)。
玉木「でも、力織機ですごくよかったなって思うのは…見てわかるんですよ、どこが悪いのかが。その後のレピア織機とかジャカード織機だと、電子的な部品がいっぱい付く感じなんですよ。だから、動きを追えないの。でも力織機って全部のパーツが鉄で、鉄の塊だから。このボタンを押したらここが作動してさらにこっちが動いて…って、様子を観てたら全部わかるの。どう動かしたいかは機械に訊けた。」
—— はい。
玉木「だから、自分が動かしたいように動かすにはを、織機と対話出来るというオモシロさがあって…それが楽しかったの。」
—— こうしたらこうなるという動きが手に取るようにわかると。
玉木「パーツが壊れて伊藤先生に頼んで直してもらって、というのも散々やったんですよ。乱暴だったのか、私の使い方が悪かったんだろうとは思うけど(笑)、そこを、伊藤先生と二人三脚で進んで行けたから、あの力織機で、他所にはない唯一無二だと思える、一生創り続けたいというショールを創ることが出来たから…それは伊藤先生のおかげですよ。」
—— 力織機を手に入れた当初からカスタム化していったところはあるんですか?
玉木「力織機自体はまんま使ってます。あるモノを活かすというスタンスでしか、やりたくないな、と思った。」
—— そのまんまの織機のポテンシャルを引き出すと。
玉木「特に、大柄にしたい人なので、私は。細かい柄は嫌だから、横の柄を出すってゆうのに一番苦戦した。生地の組織ももちろんだけど、柔らかい風合いにどうやってするか?ってゆうのを、元々備わっていた力織機のパーツを駆使して、最大限柔らかい織り方を模索して。横糸の柄の作り方にしても、その鉄板みたいなパーツの種類が限られているのよ。だから無限には柄を創れない。今手元にある鉄板を使って、最大限長くてリピートのない柄をどうやって創るのか?の3ヶ月だった。」
—— 力織機のポテンシャルを自分が望むように最大限引き出すような試行錯誤だったという。
玉木「色もね。再現性の無い柄になるように、どう出来るか?ってゆうのは…いわば、この力織機を使った、誰もが出来ないことを私がやるのにはどうしたら良いか?をずっと考えてた。」
—— なんというか…唯一無二というところの…
玉木「私でしか出来ないモノでないと、わざわざ織機を導入した意味もないし、西脇でこれをやる意味もないから、そこへの追求だけは妥協したらアカンなと思って3ヶ月間やり続けました。」
—— その場に伊藤先生が毎日のようにいらしたと。
玉木「しょっちゅう付き合ってもらった。ヘンな音する!シャトルが飛び出る!っとか。そんなんばっかり(笑)。」
—— はぁ~。。
玉木「感覚的に使ってるから不具合の理由はわからないんですよ…。力織機とはなんぞや?、という理屈も勉強してないし。皆さん学校とかでちゃんと学んだ上でやってるわけですけど、テキトーに動かしてたらあれ?シャトルが飛び出すな、オカシイなと(笑)。その度に伊藤先生が直してくれた。」
—— 古い織機なのでマニュアルも説明書もないわけですよね。とりあえず実践でやってみて…
玉木「とりあえず動かしてみた。簡単な構造原理は聞いたけど…経糸が手前にやってきて、緯糸がポンポン飛ぶから機が織れて行くんだ、と。だけどやっぱり私がやっていたのはあくまでも研究とデザインだったから。機械のメンテナンスに関しては、本当に伊藤先生にドップリだった。経験が無いしなぜ動かないのかわからないから、常に伊藤先生を呼んで訊くってゆう日々を延々続けてましたね。…だから、いてくれなかったら、織れなかったと思う。」
—— そもそも、そんなアプローチをするデザイナーっていなかったでしょうね。
玉木「たぶんね…。いなかったと思うよ。」
自らの手で織機を操り生地の感触を確かめ、試行錯誤し研究を重ねながら想いのままに創作を繰り広げる。
玉木の体当たりなモノづくりの方法論は、彼女ならではの、前例なき、唯一無二のものだったと言えるだろう。
—— “空前絶後”というか…。播州織に限らず、かつての工場での女子従業員の方々の役割にしても決められた通りのやり方で…
玉木「指示書通りにいかに織るかだからね。」
—— そうじゃなくて、やってみたいからやってるという…
玉木「触らせて!って言って。」
—— 伊藤先生はそれを面白がって…
玉木「うん。一緒にやってくれた…。」
—— 二人三脚でやってくださったという。
玉木「もう嫌や、って怒られたことはない。」
—— 改めてそう考えると、tamaki niime の歴史の中でも…
玉木「重要人物。だって、これまで織るメンバーはかなり変わって来てるわけですよ。私から始まって、代々色んなスタッフが携わって来たにも関わらず、伊藤先生はずっといてくれたから。ホントに私にとっては「織チーム」の柱みたいな存在だった。」
—— はい。
玉木「だから私にとっては伊藤先生がいなくなったことってすごくダメージが大きくて。あぁ……ってなるじゃないですか?もういざという時にメンテナンスしてもらえる人がいないってことだから…。」
—— 掛け替えのない存在…
玉木「もちろんお元気な間にちゃんと引き継ぎなさいとは言って来たよ。だから、これからウチのスタッフがどれだけ教えを受け継いでいるかが実際に見えてくる。活躍していってくれるとは信じてるけど、伊藤先生みたいに出来るかどうかはまだわからないよね。」
—— …。
玉木「西角さんとかにも助けてほしいとお願いして。でもその時に言われたのは、俺は教えへんど、と。まずは説明書を読め、と。力織機にはないけどレピア織機ならあるから。まずは読んで自分で理解しようとして、その上で使ってみてわからないことに関しては、訊いたら答えてやる、と。でも座ってたら先生が教えてくれるというもんやないど、と。おっしゃる通りですと。その意思を持って、皆んなが「織」を出来るか?今までは先生、先生と、伊藤先生を呼んだら助けてもらえたから。何か機械がおかしいんです、うまく織れないんです、って頼ったら…のび太にとってのドラえもんみたいな存在だったわけじゃないですか?」
—— 答えがポンっと、ドラえもんのポケットならぬ、伊藤先生の技術の引き出しから出てくるみたいな…。
玉木「そう。ここが問題だよ、って教えてくれて、しかも直してもくれる人だったのが…ドラえもんがいなくなったのび太ってやばいじゃないですか?(笑)」
—— 自力でなんとかしないと、という。
玉木「そう。だから“緊急事態宣言”を出して、茶谷と藤本、かつての「織チーム」のスタッフ2人も復帰させた。2人とも伊藤先生から引き継いでいるものがあるだろうと。他の業務もあるけれど、メンテナンスも含めて、谷口君と九後さんだけでは大変だから、一緒にやっていってほしいと。体制を変えました。」
—— 伊藤先生のお弟子さんが結集して。
玉木「もう自分たちでやって行けってことだから、ちゃんとしなければいけないなと思って。…ここ1、2年で伊藤先生もそうだけど、初子さんでしょ、國男さんでしょ…やっぱり、背中で見せて来てくれた私たちの親的存在がいなくなって、やるべきことを自分でやれ、と。私たちの世代がちゃんとやって、下の世代に見せていかなきゃいけない、というバトンを受け取るタイミングなのだろうなぁと。」
—— 色んなtamaki niimeからの頼まれ事が伊藤先生にとっては嬉しかったんでしょうし、大きな意味でいえば、播州織というこの地域の文化を若い世代に引き継いでもらえているという実感があったんだと思います。
玉木「家族の人たちを連れてきてくれてたらしくて。lab案内して、織機を動かして。カッコつけて見せびらかしてたそうだから(笑)、自慢ではあったんだろうね。」
—— 誇らしげに…。
玉木「色んな処に出かけてはウチを宣伝してくれたり、逆に今治にある「タオル美術館」という、タオルの製造工程が一度に観れるミュージアムがあるんですけど、無茶エエから行って来たらいいぞ、って教えてくれたり、谷口君を一緒に連れてってくれたりだとか。」
—— 人脈を活かした広報活動も。メンテナンスの技術者に留まらずに…
玉木「そう。違うねん。色んな人を連れてきてくれたりだとか…。」
—— それもまた人づてのご縁ですよね。
玉木「そう。ホントに伊藤先生はじめ、そんな方々に囲まれていたからこそ、今まで続けて来られたんだな、って思いました。西脇でモノづくりを始めた当時はSNSをガッツリやってたわけじゃないし、色んな人が人を連れてきてくださって、またその人が人を連れてきてくださって…ずっとその連鎖だから。これからも、このshop&labが、わざわざ連れて来たいと思ってもらえるような場所であり続けないとそれは成し得ないと思うし…。」
—— …。
玉木「…伊藤先生、面白がってくれたんだろうね?」
—— ……お話を聞いて、やっぱり良い意味で“クレイジー”な人だったんでしょうね。「589」から「上野」のshop&labへ、そして今やそれこそミュージアムみたいに色々な織機が並んでいるここへの移動なんかも伊藤先生が?
玉木「伊藤先生が陣頭指揮をとって何人かのチームプレーでガーンと動かしてもらって、やってくれました。どんどん伊藤先生みたいに機械を熟知されている人が少なくなってゆくのと、たまたま土田さんとの出会いがあって、この力織機に巡りあって、岩間織機制作所というメーカーの機械なんですけど、これは播州織産地の中ではレアな織機らしいんですよ。やっぱりメーカーによって機械の構造やパーツが異なるから、伊藤先生が要で。その存在がいなくなった後、どう補っていくかは手探りでやって行くしかない、頑張ろう、って感じですね。」
—— 伊藤先生のメンテナンス力、技術力というのも、替えのきかない、“唯一無二”というか。
玉木「いやホント、誰もいないですね。機料店さんに訊いても、伊藤先生の替わりになるような人は?…おらん、他の産地には?…おらん、って。だから他にも伊藤先生を頼りにしていた高齢の機屋さんたちもどうしよう?って言って、困っている。だって84歳で現役だったってことは、よっぽど誰もおらんって事でしょ?」
—— 昔の力織機まで扱える人ってなったら本当に限られてくるって話ですね。
玉木「まずいないんですよ、力織機を扱える人が。世代的に力織機の経験があるのは西角さんの世代、70代後半くらいまでだね。」
—— そうなんですね…。
玉木「まぁ力織機は最悪の場合、稼働を終えて飾ることにするとしても、レピア織機やしっかり動いてる織機はずっと使っていきたいし、最後に伊藤先生が良い機械をと、ジャカード織の織機を新たに入れてくれたのが整備途中なので…先生としてはやり残した感が一杯で、早くtamaki niimeに行かな、ってずっと言ってたって。」
—— それはお亡くなりになる前に?
玉木「しばらく休んでいて、ウチに久しぶりに来た日があったんです。そこで私も話が出来て。だいじょうぶ~!??って言って。「もう、はよtamaki niimeに行ってメンテやらな、行きたくてしゃあなかった。」って。だから、「引き戻されたね…。」って話してたの。」
—— 最後まで、tamaki niimeの織機たちを気にして…
玉木「これからまだ正念場ですよ、私たちの。織を続けられるのか?まあ、伊藤先生が見守ってくれてるとは思います。残された若者たちの力量が試されている2025年ですね。」
—— そこは伊藤先生のお弟子さんたちが。
玉木「やるしかない。乞うご期待!って感じです。」
“愛弟子”と呼べる谷口希望にもこの場に来てもらい、「伊藤先生」を語ってもらった。
谷口「本当に、公私ともに無茶苦茶お世話になっていたので、もう、これからどうしよう…?ではあるんですけど、出来るように、やるしかねぇわ!と。まだまだ教えてもらい足りなかったんですけど、受け取ったものを絶対に無駄にしないように、頑張りたいと思っています。」
—— 公私ともに。
玉木「だって、家にも織機置いてるからさぁ。それも岩間のなの?」
谷口「岩間のやや小さめの。」
玉木「そうなの?伊藤先生の跡取りは谷口君や。岩間のことならオレに聞け、と(笑)。」
谷口「休みの日に日生の方に、よし、牡蠣食いに行くぞ~!」って遊びに行かせてもらったりもしました…。」
—— 伊藤先生の遺されたジャカードの織機をただ今メンテナンス中だとか?
谷口「はい。」
玉木「たぶんすぐ隣で見てくれてるよ。あとは皆んなが頑張ってくれますから、愉しみにしましょ!」
最後は酒井に締めてもらおう。
酒井「伊藤先生は、もう亡くなられたけど、播州織産地に残っていた最後の天才であり異端児だったと思います。常に新しいことにチャレンジしようとする人で、良い意味で前のめりだった人なんで。」
—— エネルギッシュな人だったと聞きました。ずっと動いてる人だったと。
酒井「そうなんスよ。だから、稀有な人っていうか。いなくなってみないとその偉大さがわからない。残された僕たちがどう引き継いで行くか?伊藤先生は「走る人」。最後まで走ってた人でした。」
織機の音が響く「織」の現場はtamaki niimeのモノづくりの心臓部だ。
そこは、播州織の歴史とともに歩んだひとりの型破りな機械職人が、終の住処にするように、己れの生命を燃焼させた場所でもあった。
留まらず最後まで疾走を続けた伊藤義忠さん。「伊藤先生を偲ぶ会」は1月16日(木)の夜、tamaki niime tabe roomにて、長年故人と関わって来た産地の人たちも集まり行われた。
会場に設られた大型モニターには、スタッフとともに織機と戯れる「伊藤先生」の笑顔が繰り返し繰り返し映し出されていた。
Original Japanese text by Seiji Koshikawa.
English translation by Adam & Michiko Whipple.